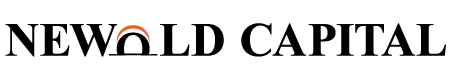M&Aを検討する上で欠かせない存在であるSPCの活用。しかし、「名前は聞いたことがあるが詳しくは知らない」「SPVやTMKとの違いがよく分からない」という方も多いのではないでしょうか。
この記事では「SPCとは何か」といった基本的な情報から、設立するメリット・デメリット、実際にSPCを活用された事例まで解説します。
Contents
- 1 その名の通り“特別な目的”のために設立される! ──SPCとは?
- 2 SPV・SPAC・TMKとの違い
- 3 リスク分離や大規模な資金調達に有効! ──SPCが活用されるのはどんな時?
- 4 リスク分離や国際的な活用にも◎ ──SPCを活用するメリット
- 5 コスト面や債務リスクに難あり…!? ──SPCを活用するデメリット
- 6 SPC設立の流れを5ステップで詳しく解説! ──SPCの設立方法
- 7 TMK、GK-TK、REITについても理解できる! ──SPCを活用した主なスキーム
- 8 SPC活用のイメージをより具体的に! ──SPCを活用した実際の事例
- 9 SPCを上手く活用すれば、効果的な資金調達ができる!
その名の通り“特別な目的”のために設立される! ──SPCとは?
SPCとはSpecial Purpose Companyの略で、日本語に翻訳すると「特別目的会社」となります。その名の通り、特別な目的のために設立される法人のことです。ここでいう「特別な目的」は、主に事業ごとの資産管理や資金調達などを指します。
具体的には、企業の特定の資産を切り離して運用することで、事業リスクの分散や資金調達の効率化、投資家による投資などを促します。一般的に、不動産投資、M&A、プロジェクトファイナンス、証券化などで活用されることが多いです。
日本では1998年に法律が確立され、SPCの仕組みを使えるようになりました。当初は「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」と呼ばれるものでしたが、2001年に「資産の流動化に関する法律」という名称に変更。その際、すべての財産権が対象となり、手続きも簡素化され、以前より利用しやすい仕組みになりました。
SPV・SPAC・TMKとの違い

よく混同されがちなのが、「SPV」「SPAC」「TMK」といった仕組みです。一見似ているように見えますが、プロセスや目的が異なります。それぞれの特徴を比較してみましょう。
SPV(Special Purpose Vehicle/特別目的事業体
債権や不動産の流動化、証券化など、特定の資産を保有するためだけに設立された法人全般を指します。資産管理や証券化など、用途は多岐にわたるのが特徴です。SPCは、このSPVの一種と位置付けられます。
SPAC(Special Purpose Acquisition Company/特別買収目的会社)
未公開企業の買収を目的とした上場会社で、投資資金を集めるために設立される法人です。自社事業を持たないペーパーカンパニーとして設立され、買収を通じて未公開企業を実質的に上場させる仕組みです。
現在の日本では、まだSPAC上場は制度として認められていませんが、金融庁や東京証券取引所を中心に制度導入に向けた検討が進められており、今後1~2年以内の導入が見込まれています(2025年4月時点)。制度が整えば、日本でもスタートアップや中堅企業の新たな上場ルートとして注目される存在になると考えられています。
TMK(Tokutei Mokuteki Kaisha/特定目的会社)
「資産流動化法」に基づいて設立される法人で、不動産や債権などの資産を証券化するために用いられる、特別な会社形態です。特に、特に大規模な不動産取引や、不動産ファンド・REIT(不動産投資信託)との連携でよく利用されます。
| SPV | SPC | TMK | SPAC | |
|---|---|---|---|---|
| 日本語訳 | 特別目的事業体 | 特別目的会社 | 特定目的会社 | 特別買収目的会社 |
| 主な用途 | 資産管理、証券化、ファンド運用 | ファンド・M&A | 不動産・債権の流動化 | 未上場企業の買収・上場支援 |
| 形態 | 法人格あり/なし(信託含む) | 法人格あり(会社法に基づく) | 株式会社(資産流動化法に基づく) | 株式会社(上場企業) |
| 主な活用場面 | 不動産、ファンド、証券化、PE投資など | LBOスキーム | 不動産証券化 | スタートアップの上場支援 |
ペーパーカンパニーとは何が違う?
「SPC=ペーパーカンパニー」と認識される方も少なくないでしょう。確かに、事業活動の実体がないという点ではSPCもペーパーカンパニーと共通しているかもしれませんが、厳密には異なります。
ペーパーカンパニーとSPCの違いは「会社自体が目的を持って設立されているかどうか」という点です。
そもそも、ペーパーカンパニーという言葉自体に法的な定義はありません。ただ一般的には、「登記上では設立されているが、事業活動の実態がない形式的な企業」を指します。会社自体に目的はなく、租税回避や節税目的で設立されることが多いです。
一方、SPCは事業運営や資産管理、資金調達など、合法的かつ特定の目的のために設立されます。このように特定の目的を持って設立されているという点で、ペーパーカンパニーとは異なるSPCならではの特徴と言えるでしょう。
リスク分離や大規模な資金調達に有効! ──SPCが活用されるのはどんな時?
SPCは、特定の資産や事業を切り離して管理し、資金調達を効率的に行うために活用されます。主に以下のような場面で利用されることが多いです。

・リスク分離が必要な場合
・大規模な資金調達が必要な場合
・資産の証券化を行う場合
特にM&Aや不動産投資での利用が多くなっています。それぞれの活用方法について詳しく見ていきましょう。
M&AでSPCが活用されるケース
M&AでSPCが活用されるケースを具体的に見ていきましょう。
LBO(レバレッジド・バイアウト)での活用
LBOとは、投資家から調達した資金をSPCに入れ、その資金と借入を合わせて対象企業を買収する手法です。
特にPEファンドがM&Aを行う際に多く利用されます。
PEファンドについてはこちらの記事をチェック!
LBOについてはこちらの記事をチェック!
LBOを活用することで、自己資金のレバレッジ(投資効率)を最大化しながら、企業買収を実現できます。というのも、M&AでSPCを利用する場合、SPCが代わりに資金調達を行うため、買い手自体は買収にかかる資金調達のリスクを負わずに済むからです。
また、LBOでは、買収・合併後の会社(譲渡企業(売り手)とSPCの統合体)が金融機関への借り入れを返済することが前提となっています。買収する側であるSPCは、対象会社の株式を取得するために、プレミアム(上乗せ価格)を提示することが一般的です。
※本コラムでは、説明をわかりやすくするために、「譲受企業」を「買い手」、「譲渡企業」を「売り手」と表現します。
MBO(マネジメント・バイアウト)での活用
MBOとは、経営陣が自社の株式を取得し、企業を独立させることです。MBOでもSPCが設立される場合があります。MBOにおいても、SPCの設立は円滑な企業買収を進める上で有効です。
企業の買収において、多額のお金が動くケースも少なくありません。その際、後継者個人の信用力だけでは、買収に必要な資金を全額借りることは難しいです。そこで、SPCと売り手が合併することを前提にSPCを設立します。その結果、後継者は売り手の信用力を利用して、ローンを調達することができるのです。
資産を移転するスキームとしての利用
不動産や知的財産などの資産のみを売却する場合においても、SPCを利用できます。具体的には、SPC設立を通じた資産管理を行うことで、対象資産を明確にし、売却をスムーズに進めることが可能です。特に不動産投資ファンドなどで活用されています。
不動産投資でSPC・TMKが利用されるケース
不動産事業・投資においては、SPCを活用することで投資家から資金を調達し、不動産を運営することができます。具体的には、SPCは特定の資産を切り離せるため、SPCに不動産のみを売却します。その後、SPCが不動産を担保に金融機関から資金調達を行うという仕組みです。
また、大規模な不動産や開発は莫大な資金が必要となり、資金力のある投資家に限られてしまうという課題も、SPCの活用で解決できます。
というのも、SPCが不動産からの収益を裏付けとして有価証券を発行することで、不動産を小口化し証券化することができます。その結果、少額からの投資が可能となり、より多くの投資家から投資を募ることができるのです。また、投資家への収益還元も容易となります。 加えて、税制メリットがあるのも特徴です。不動産流動化の場合、SPCではなくTMKが設立されるケースが一般的です。その場合、法人税については二重課税を回避するための特例措置が設定されています。そのため、投資家に対する配当金においては損金算入すれば法人税を控除することが可能です。
リスク分離や国際的な活用にも◎ ──SPCを活用するメリット
SPCの活用には、以下のようなメリットがあります。

① 資金調達のしやすさ
② 親会社からの倒産隔離(リスク分離)
③ 資産のオフバランス化(財務負担の軽減)
④ 国際的な適用性
⑤ 投資リスクの軽減
⑥ M&A戦略の柔軟性
① 資金調達のしやすさ
SPCを活用することで、多くの投資家から出資を募ることができます。また、銀行借入に依存せず、LBOや証券化を活用しながら最適な資金調達を実現できます。具体的には、SPCは特定の資産を担保に金融機関から融資を受けることが可能です。さらに、投資家から広範囲にわたり資金を募ることができます。
また、金融機関がSPCに対して融資を行うかどうか判断する際、親会社の信用力ではなく、SPCの資産や事業の収益力に基づく信用力で判断されます。そのため、親会社の信用力が低い場合でも、SPCの信用力に基づいて融資可否が判断され、資金調達を実現できるのです。
② 親会社からの倒産隔離(リスク分離)
SPCを通じて資産や事業を切り離すことで、親会社の倒産リスクの影響を受けにくくなります。与信判断の影響を回避し、投資家にとって安全性が向上することが特徴です。というのも、SPCは親会社の資産や負債とは独立した存在として設立される法人です。SPCの設立には特定の資産が出資され、その資産をもとに活動が行われます。
そのため、親会社が万が一倒産した場合でも、SPCが保有する資産は親会社の債権者による差し押さえの対象にはなりません。親会社に問題が発生しても、親会社の経営状況から分離された状態を保つことができるのです。
このような構造により、金融機関や投資家は親会社の信用評価を気にすることなく、SPCが取り扱う特定の事業の収益力や将来性のみを基準に融資判断を行うことができます。
つまり、SPCを設立することで、より透明で公平な評価が可能となり、投資リスクを軽減しつつ、事業活動に必要な資金調達をスムーズに行うことができるのです。
③ 資産のオフバランス化(財務負担の軽減)
オフバランスとは、資産や負債が存在していてもBS(貸借対照表)に記載されないことを意味します。SPCを活用することで、特定の資産を親会社の財務諸表から分離し、負債比率を抑えることが可能です。
SPCの設立により、親会社の財務諸表から特定の資産や負債を切り離すことができます。その結果、親会社の財務状況を悪化させずに、特定の事業に必要な資金を調達することができるのです。例えば、M&Aの実行にあたり、巨額の負債が発生する場合でも、その負債はSPCのものになるので、親会社の財務状況への影響を最小限に抑えることができます。
親会社の経営から切り離して処理することで、財務状況を圧迫せずに事業活動を円滑に進めることができるため、SPCの設立は大きなメリットと言えるでしょう。特に不動産事業やM&Aのように、多額の負債が発生する可能性のある事業においては、このオフバランスの手法は非常に有効です。
④ 国際的な適用性
海外でSPCを設立する場合、その国の法制度を活用できるため、税制や規制のメリットを享受しやすいという特徴があります。いわゆるタックスヘイブンをはじめ、設立国の制度が利用できるだけでなく、海外で事業を展開する場合にも効果的です。 ただし、特定のSPC(TMKなど)は設立法律に基づき、海外での設立が制限される場合や、期待した効果が受けられない場合があります。海外でのSPC設立を検討する場合は、専門家のアドバイスが必要となるでしょう。
⑤ 投資リスクの軽減
SPCの設立は、投資家にとってもメリットがあります。リスクをSPCに限定することで、投資家のリスク負担を最小限に抑えられるのです。
具体的には、SPCは親会社とは独立した存在であるため、特定のプロジェクトや事業に関連するリスクを分散できます。これにより、投資家は親会社の経営リスクから解放され、SPCのみに焦点を当てた投資が可能です。投資リスクが低減し、安全な投資環境が提供されます。
また、特定の事業のみに焦点を当てることで、財務状況や事業計画も明確になりやすく、投資家は資金の使途や収益の見通しを把握しやすくなることが期待できます。より透明で信頼性の高い投資判断が行えるでしょう。 加えて、親会社の財務状況に左右されることなく、特定の事業の収益力や将来性を基準に資金を調達できるため、純粋に事業の魅力に基づいて投資できる点も魅力です。
⑥ M&A戦略の柔軟性
SPCを活用することで、事業売却や買収のスキームを最適化できます。自己資金が少なく済むので、レバレッジがかかりやすいのが特徴です。M&Aが成功すると、自己資金でM&Aを行うよりも、高い利益率を上げられる可能性があります。
コスト面や債務リスクに難あり…!? ──SPCを活用するデメリット
SPCの設立にはメリットがある一方で、以下のようなデメリットも存在します。

① 設立・運用に手間とコストがかかる
② M&Aの際、買収後に債務が残るリスク
③ 借入による返済不能リスク
④ 悪用されるリスクがある
① 設立・運用に手間とコストがかかる
SPCの設立には多くのメリットがある一方で、設立・運用にかかる手間やコストは大きなデメリットとなります。
まず、「手間」の面では、SPCを設立するための手続きは非常に煩雑です。信託銀行・税理士・弁護士・司法書士・公認会計士など、様々な専門家に設立業務を依頼したり、投資家と出資契約ができる環境を整えたりする必要があります。また、SPC法に基づいて設立する場合、内閣総理大臣への届出や業務開始届出、資産流動化計画などの手続も求められます。
「コスト」の面では、そもそもSPCを設立する段階で、資本金や登録免許税などの初期コストが発生します。加えて、SPC設立における検討や手続きは専門家に依頼することが一般的であるため、弁護士や司法書士への報酬の支払いも必要です。投資家との契約や金融機関への打診においても、コストがかかることを視野に入れておくべきでしょう。
また、SPC法に基づいた設立の手続きを行う際は、一般の会社法との違いを認識しておく必要があります。
例えば「会社法の最低資本金は1円から、SPC法の最低資本金は10万円から」といった違いです。詳細は「SPC法と会社法との違い」の項目で後述します。
なお、第三者の出資を得てSPCを設立する場合には、資産の売却益を、出資の割合に応じて第三者に渡す必要があります。売却益の全てが入るわけではないので注意しましょう。 会社として運営する以上、一定の資金は少なからず必要になります。「SPCの設立が本当に手間とコストに見合うのか」「本当にまとまった資金調達が実現できるのか」など、専門家に相談しながら十分に検討しましょう。
② M&Aの際、買収後に債務が残るリスク
SPCを通じたM&Aでは、買収対象の企業が負債を抱えるケースがあり、買収後の財務リスクが残る可能性があります。
SPCで調達した資金を用いてM&Aを実施する場合、SPCと売り手を合併させた会社に、過大な債務が残るケースがあります。これは、資金調達時に負った債務の返済義務を売り手が負う仕組みになっているからです。 SPCを用いたM&Aには債務が残るリスクがあることを、あらかじめ理解しておくと良いでしょう。
③ 借入による返済不能リスク
SPCは資金調達のために借入を行うことが多く、収益が想定通りに上がらない場合、返済が困難になるリスクがあります。最悪の場合、倒産に陥ってしまう可能性も否定できません。
もし、業績不振などで当初予定していたキャッシュ・フローが得られず、借入額を返済できなくなった場合、倒産となってしまいます。そのため、慎重に検討を進める必要があります。
④ 悪用されるリスクがある
SPCは透明性が求められますが、場合によっては資産の隠蔽や租税回避目的で利用され、不正に使われる可能性があります。
SPCは会社資産の貯蔵庫です。親会社が持つ価値のない不動産・不良債権・回収できない売掛金など、不要・不都合な資産をSPCに押し付けることができます。その結果、貸借対照表を改善し、本社の業績を良く見せることができてしまうのです。
このようにSPCを利用した悪用は「飛ばし」と呼ばれています。
実際、過去には粉飾決算を行った事例も存在します。最も有名なのは、アメリカで起きたエンロン事件です。大手エネルギー会社のエンロン社は、株式市場からの信頼が高い企業でしたが、実際は損失をSPCに簿外債務や売上の水増しを繰り返していたことが明らかになりました。その後、わずか2ヶ月で160憶ドル超とも言われる債務超過から倒産しています。
また、日本においても2006年に日興コーディアルグループがSPCの連結除外を用いて巨額の評価損を回避した事件が起こりました。2011年にはオリンパス社が資産運用や投資の失敗による損失を海外に設立したSPCに移し替える事件も起きています。
現在は法改正により、「支配関係にあるSPCは、本社と連結していなければならない」など、飛ばしができないようになりました。とは言え、運用方法には細心の注意が必要です。
SPC設立の流れを5ステップで詳しく解説! ──SPCの設立方法
実際にSPCを設立する場合、以下のような手順で進めます。

Step1 事業目的の明確化
Step2 会社形態の選定
Step3 資本金の決定
Step4 設立登記の申請
Step5 運用・会計管理の体制構築
各プロセスについて、流れやポイントを詳しく見ていきましょう。
Step1 事業目的の明確化
まず初めに、どのような目的でSPCを設立するのかを決定します。ここでは、M&Aの場合と不動産事業・投資の場合に分けて、具体的にどのような目的があるのか見ていきましょう。
M&Aの場合
M&AにおけるSPCの設立には、「買い手などが特定の資産をSPCに出資し、買収に必要な資産を切り分ける」という目的があります。これにより、親会社の財政負担を避け、経営上のリスクを回避できるのです。また、買収先の企業価値や切り分けた資産を担保に資金調達を実施するため、買い手の財務リスクを大幅に軽減できます。
さらに、SPCを活用したM&Aでは、LBOのスキームを使うことが一般的です。LBOでは、借入資金の返済は対象会社がSPCと合併して行うため、親会社は財政負担がなくリスクを抑えることができます。
不動産事業・投資の場合
不動産事業・投資におけるSPCの設立では、「SPCに売却した不動産を担保に金融機関から融資を受け、資金調達を行う」という目的が代表的です。不動産自体の価値に加え、将来生み出す収益を見込んで証券化し、資金を調達することができます。
不動産事業を証券化すると、小口の投資家からも多く募ることで多額の資金を集めることが可能です。そのため、大規模な資金がなくても、不動産事業・投資が実現できます。
Step2 会社形態の選定
SPCの中でも合同会社にするか株式会社にするかなど、適切な法人形態を選びます。
まず、合同会社・株式会社についてですが、それぞれ以下のような特徴があります。
| 合同会社 |
– 特徴 – ・法人税制上の優遇があり、設立や管理が比較的簡単。 ・出資者の責任が有限であるため、リスクが限定される。 ・簡便で柔軟な運営が求められる場合や、少人数の出資者で構成される場合に適する。 |
| 株式会社 |
– 特徴 – ・出資者が多くても管理しやすく、株式市場での資金調達が可能。 ・信頼性が高く、広範なビジネス活動に対応できる。 ・大規模な事業や多くの投資家を集めたい場合に適する。 |
また、TMK(特定目的会社)、GK-TK(合同会社―匿名組合)、REIT(不動産投資信託)といった形態については、SPCを活用した主なスキームの項目で詳しく解説しますが、それぞれ以下のような特徴があることを覚えておきましょう。
| スキーム | 特徴 |
|---|---|
| TMK(特定目的会社) | ・SPC法で設立され、利益を創出できない ・税的メリットや取得資産に制限がない |
| GK-TK(合同会社―匿名組合) | ・匿名組合や金融機関から資金調達を実施 ・海外の投資家などからも資金調達ができる |
| REIT(不動産投資信託) | ・主に不動産投資に用いられる ・証券化により、小口の投資家からも資金調達を募りやすい |
上記の特徴を踏まえて、専門家に相談しながら自社の目的や状況に適した会社形態を選択することが大切です。
Step3 資本金の決定
設立に必要な資本を調達します。調達方法の一例は、以下の通りです。
銀行融資
SPCの資金調達方法として最も一般的なスキームです。銀行はプロジェクトのリスクを評価し、融資額を決定します。
社債発行
社債を発行して資金を調達することも可能です。投資家に利息を支払うことで、必要な資金を集めることができます。
株式発行
株式を発行することでも資金を調達できます。投資家は株式を購入することで、SPCの所有権の一部を取得します。
プロジェクトファイナンス
特定のプロジェクトに対して資金を調達する方法です。プロジェクトの収益を担保として融資を受けることができます。
投資ファンド
PEファンドやベンチャーキャピタルなどの投資ファンドから資金を調達できます。大規模なプロジェクトでも必要な資金を確保できる点が特徴です。
政府補助金・助成金
政府や地方自治体から提供される補助金や助成金も資金調達の一つの手段です。特に公共性の高いプロジェクトに対して支給されることが多いです。
キャッシュ・フローの活用
既存のキャッシュ・フローを活用した資金調達も可能です。プロジェクトの収益や運営から得られるキャッシュ・フローを使い、追加の資金を調達します。 SPCの資金調達方法は、プロジェクトの規模やリスクプロファイル、投資家のニーズに応じて選択します。どの方法が最適か判断する際は、専門家の助言を受けると良いでしょう。
Step4 設立登記の申請
法務局への登記申請を行います。SPCの設立・登記方法や手続きは、基本的に普通の株式会社設立の場合と変わりません。SPC法に基づくか、会社法に基づくかにより、資本金の金額や一部の手続きが変わります。詳細は「SPC法と会社法との違い」の項目にて後述します。
SPC法は「資産の流動化に関する法律」とも呼ばれています。資産の価値を利用して資金調達がしやすくなるのが特徴です。ただし、資産流動化計画と業務開始届を作成しなければ業務開始ができないので、注意しましょう。
一方、会社法に基づいて設立する場合は、株式会社よりも合同会社として設立するほうが全体的なコストや手間を省くことができます。そのため、合同会社として特別目的会社を設立するケースが一般的です。
いずれの方法にせよ、弁護士や司法書士などの専門家に相談したうえで検討しましょう。
Step5 運用・会計管理の体制構築
税務処理やガバナンスの整備を行います。
まずは、資金流動化計画の作成や事業開始届を提出するために、信託銀行・弁護士・公認会計士・税理士などと調整をしましょう。買収後は、企業同士の事業承継・会計処理・許認可の維持取得などを実施します。また、自己資本利益率が低下しないようにするためには、事前の制度設計も非常に重要です。
【運用のポイント】
◎税務処理の適正化
SPCの会計処理や税務申告を適切に管理します。例えば、貸借対照表や損益計算書の作成、支払配当の損金算入、個別での所得税申告、税務上のリスク管理などが挙げられます。
また、「一定の要件を満たす場合、連結納税の対象外となる」「支払配当の損金算入制度を利用できる」「一部の場合を除き、外形標準課税の対象外となる」といったSPCならではの特徴も抑えておくと良いでしょう。
◎会計監査の対応
設立後の財務管理を適切に行い、投資家や金融機関に透明性を確保します。会計監査の目的は、SPCの財務情報が正確かつ公正に報告されているか確認することです。監査人は、財務諸表や関連する会計記録を検証し、不正や誤りがないか確認します。
また、内部統制システムの評価や監査報告書の作成も行います。金融商品取引法や税務規制を遵守しているかといったコンプライアンスの確認も欠かせません。これらの結果をもとに、リスク評価やフォローアップを行うことで、運営の改善や事業成長が期待できます。
◎ガバナンスの強化
SPCの独立性を保ち、適切な経営体制を維持します。SPCの運営においては、明確なガバナンス構造を確立することが大切です。具体的には、役員や管理者の責任範囲、報告ライン、意思決定プロセスが含まれます。
また、独立した監査機能は、不正や非効率性を防ぐために重要です。内部監査および外部監査を通じて、SPCの活動が適切に行われていることを確認しましょう。
その他、リスク管理やコンプライアンスの確保、役員教育・訓練、ステークホルダー(投資家、顧客、従業員など)との対話を進めることで、全体のガバナンスが強化されます。
SPC法と会社法との違い
SPC法は資産の流動化のための法律で、SPC法によって設立される法人は、社団法人となります。一方、会社法は株式会社・合同会社・合資会社・合名会社といった会社の設立について定める法律です。
SPC設立における条件の相違点は、以下の通りです。
| SPC法に基づいた設立 | 会社法に基づいた設立 | |
|---|---|---|
| 定款印紙 | 必須 | 4万円 ※ただし、電子定款または合同会社である場合は不要 |
| 登録免許税 | 3万円 | 最低15万円 ※合同会社は最低6万円 |
| 資本金 | 10万円 | 1円〜 |
| 内閣総理大臣への届け出 | 必須 | 不要 |
| 組織構成 | 取締役1人+監査役1人が必要 | 取締役1人 ※合同会社は社員1人だけでも可 |
| 会計監査法人 | 一定の場合のみ必要 | 大会社の場合にのみ必要※合同会社は不要 |
| 設立後の注意点 | 資産流動化計画を作成し、業務開始届を提出して初めて開業できる。 | 特になし |
TMK、GK-TK、REITについても理解できる! ──SPCを活用した主なスキーム
SPCは様々なスキームで活用されますが、特に以下の3つが代表的です。
- TMK(特定目的会社)
- GK-TK(合同会社-匿名組合)
- REIT(不動産投資信託)
これらのスキームは以下の図のような立ち位置になります。

それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
① TMK(特定目的会社)
TMKとは、特定目的会社(Tokutei Mokuteki Kaisya)を意味します。日本の証券化スキームの一種で、不動産や金融資産の証券化に利用されるものです。
TMKはSPC法で設立されるため、一定の要件を満たせば、法人税の軽減が可能です。ただし、事業範囲が定められており限定的で、設立手続きも煩雑という側面もあります。そのため、TMKの活用は減少傾向なのが現状です。
投資家から出資を募る際は、投資証券の発行や匿名組合ではなく、一般的な出資契約により優先出資を募る仕組みになっています。

② GK-TK(合同会社-匿名組合)
GK-TKとは、合同会社(Godo Kaisya)と匿名組合(Tokumei Kumiai)を組み合わせた言葉です。合同会社(GK)をSPCとして設立し、匿名組合(TK)を通じて投資家から資金を集めるスキームとなっています。
GK-TKは低コストで設立可能で、投資家が匿名性を保ちつつ出資できるため、SPCを活用する手法として広く活用されています。さらに、匿名組合には法人格がないため、二重課税の問題を回避し、投資家により多くの利益を提供することができます。

③ REIT(不動産投資信託)
REITとは、Real Estate Investment Trust(不動産投資信託)を意味する言葉です。不動産を投資対象とする投資信託で、多数の投資家から資金を集めて運用します。
「投資信託及び投資法人に関する法律」(投信法)に基づき設立され、法的にはSPCではなく「投資法人」となりますが、実際にはSPCを活用して不動産資産を管理するのが特徴です。 REITでは投資証券を発行し、投資家から資金を調達します。その後、不動産からの収益(売却益、賃料収入など)を利益として獲得し、その一部を投資家に配当として還元する仕組みです。不動産の長期的な運用に適しており、高い収益性を有しています。

SPC活用のイメージをより具体的に! ──SPCを活用した実際の事例
実際にSPCが活用された事例を紹介します。
RHサクセション
~筑邦銀行が、大阪の飲食業買収を目的としたSPCに十数億円融資~
筑邦銀行は商工組合中央金庫・福岡ひびき信用金庫と共同で、SPCのRHサクセションに、M&A資金の一部を融資しました。LBOローンが活用され、融資額は十数億円と言われています。
RHサクセションは、焼肉店「松阪牛焼肉M」などを手掛けるライトハウスの買収を目的に設立されたSPCです。ライトハウスは2023年10月、農業事業を展開するトゥルーバアグリが子会社化していました。
筑邦銀行は、情報交換会「ちくぎんアグリネットワーク」を運営し、参加者が生産した福岡県産のブランドイチゴ「あまおう」を、筑邦トゥルーバファーム*を通してライトハウスに販売する考えを持っています。
*筑邦トゥルーバファーム…トゥルーバアグリと共同出資して立ち上げた合弁会社
あなぶき興産
~SPC型アルファアセットファンドを募集開始予定~
あなぶきグループの穴吹興産株式会社は、『ジョイントアルファ[Jointo α]』にて、第37号ファンドとなる「SPC型アルファアセットファンド1号」の募集要項を公開しました。
Jointo αは、地域に眠る良質な不動産への投資を活性化させることを目的とし、少額から商業施設や投資用マンションに分散投資ができる、不動産投資特化型クラウドファンディングです。
SPC型アルファアセットファンド1号は、不動産特定共同事業3号・4号事業を活用した倒産隔離スキームを活用します。Jointo αにおいて初の取り組みです。
対象物件は岡山県倉敷市の宿泊特化型ラグジュアリーホテル「ロイヤルパークホテル倉敷」です。この物件は特例事業者であるSPCが取得し、運営会社のあなぶきエンタープライズに賃貸し、賃料収入と売却時の利益を配当原資として投資家に分配します。 SPC型アルファアセットファンドでは、SPCが物件を取得し、投資家と匿名組合契約を結びます。不動産取引や契約の代理・媒介はSPCから委託を受けた不動産特定共同事業3号および4号事業者(本件では穴吹興産)が担当します。
SPCを上手く活用すれば、効果的な資金調達ができる!
SPCを活用することで、容易に資金調達ができるようになり、特定の資産を担保に多くの投資家や金融機関から資金を募ることができます。また、親会社からの倒産リスクの影響を避けられる点もメリットです。さらに、資産のオフバランス化により親会社の財務状況を悪化させずに資金調達ができます。
一方で、設立・運用には手間とコストがかかり、買収後に債務が残るリスクや返済不能リスクが懸念されます。制度設計を誤ってしまうと、M&Aや事業運営が困難になる可能性があるため、専門家と十分に協議することが大切です。
事業承継や成長戦略を目的としたM&AをフルサポートするNEWOLD CAPITALでは、経験豊富なアドバイザーが親身になってご支援します。お気軽にご相談ください。